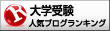いつもご覧頂きまして、ありがとうございます。KATSUYAです^^
今年の旧7帝大の数学を全て解きおえ、評価をUPしました。その総括をしたいと思います。
■総括■
1.新課程の複素数平面、条件付確率から出題は皆無
今年は新課程初年度ということもあり、これらの範囲からの出題がどうなるか気になっていたところですが、大方の予想通り、どちらもほとんど出題されず、という結果となりました。複素数平面のほうについては、難関大は大好きなので、私は出題されると思っていたのですが、来年以降となりそうです。
2.確率と漸化式がらみの問題は、今年は難。難易を繰り返す形に
東大・京大・名大等をはじめとし、今年の「確率と漸化式」の問題は難が多い印象でした。2013年度は難、2014年度はうって変わって易、2015年度はまた難です。ここ3年分は旧7帝大の問題を全て研究しておくと、「難の問題」と「易の問題」を両方見れますので、レベルの範囲が把握できます。
3.論証問題は整数からの出題が多い
整数は新課程になってからは単元として扱われるようになりましたので、傍用問題集で練習量が確保できるようになりました。それを意識したのか、ただ絞って解を出させる問題は減り、論証問題が増え、整数問題は難易度が全体的にUPしました。
■難易度順位■
ここからは、難易度順位をまとめます。
1.各問題の難易度
2.解答までの時間
3.制限時間との兼ね合いを考慮した、得点のしにくさ。
これらを綜合的に判断した結果の順位です。大問ごとに5ポイント満点で点をつけ、問題数で平均しています。
※ポイントの数値は相対的なものであり、0.2ポイント以上違えば、難易度の差が感じられるものと思ってください。
逆にいえば、それ以内の場合は、難易度の違いは人によります。
2015年 旧7帝大 理系リーグ
( )内は、昨年からの順位変動、および2013年、2014年のポイントの順)
※スマホ閲覧者を考慮し、今年から画像としました。
※評価(A~E)との目安関係 3.00pt なら、 平均して難易度C です。
特記すべき事項をいくつか。
名古屋大学が東京大学に迫る勢いで2位に浮上しました。東大はかろうじて、1位をキープしました。名大は評価点の低い問題がなく、全体的に厳しいセットです。半分なくても合格した方も多くいることでしょう。
前回躍進した九大、東北大は転落。論証系があるかどうかで、このあたりの大学は順位はかなり変動します。論証のあった京大は3位に浮上です。ただし、3位から5位はあまりポイントに差がないので、あまり変わらないかもしれません。
以上です^^