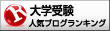いつもご覧頂きまして、ありがとうございます。KATSUYAです^^
先日の、条件を満たすベクトルと線分比の問題の解答です。
解答
(東京理科大 理工 2013)
解説
今回からベクトルに入ります。最初は、ベクトルの交点の扱いのおさらいです。この程度であれば無傷で通過しておきたいですね。
まずは、位置ベクトルに関する方程式の解法に関する原則です。
(拙著シリーズ(白) 数学B ベクトル p.32-33)
次の(2)は、交点ベクトルの扱い方に関する原則を用います。
(拙著シリーズ(白) 数学B ベクトル p.34-35)
AO:OPおよびBP:PCは、位置ベクトル等式タイプでは頻出です。作業のようにスピーディに出せるようにしておきましょう。
CO:OQについては、「CO上にあることで1-s、sの係数利用」、「AB上にあることでACの係数が0」を用いれば出せます。なお、CO:OQを分かりやすくするために、起点を一時的にCに書き換えています。
(3)は平行なので、実数倍です。CO:OQの情報がそのまま使えますね^^ (4)は(2)のBP:PCの情報も利用すればできます。答案では丁寧に書きますが、答えだけであれば、1:1という情報(合計で2)と、3:2という情報(合計で5)があるので、全部で10の長さだとして計算していけばOKでしょう。
2.解けなくて、原則を知っていた人は、思考時間を長くする演習をしましょう。
3.解けなくて、原則も知らなかった人は、原則集めからやる必要があります。
Piece CHECKシリーズでは、出来あがった答案からは見えない部分を解説していくことで、「なぜそうやって解くのか」「いったいどこからそんな答案が生まれるのか」に答えていきます。
関連する拙著シリーズなど
注:拙著シリーズは、 アマゾンのIDからでも購入が可能になりました。
注:また、販売先のサイトはクレジット決済に対応し、利便性が向上ました。
NEW!!
姉妹サイトでは、高校数学の参考書に関する情報を書いています^^
※受験ランキングに参加しています。「役に立った」という方は、クリックしていただると、すごくうれしいです^^