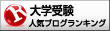●2015年大学入試数学評価を書いていきます。今回は九州大学(文系)です。 2015年大学入試シリーズ第31弾。 問題の難易度(易A←→E難)と一緒に、典型パターンのレベルを3段階(基本Lv.1←→高度Lv.3)で書いておきます。 また、☆は、「解くとしたらこれがいい」というオススメ問題です。 D・・・難関大学でも難しい部類の問題。 E・・・超高校級の難問。試験場では即捨てOKの問題。 また、解答までの目標時間を、問題ごとに書きます。※目標時間=解き方を含め、きちんと完答するまでの標準的な時間です。 したがって、目標時間を全部足すと、試験の制限時間を越えることも、当然ありえます。 同時に、その時間の2倍考えてもまったく手がつかない場合は、ヒントや答えをみるといい という目安にしてください。 九州大学 文系数学 昨年より易化。文理共通の問題も、文系ではかなり負担が軽くなっています。残りの問題も、やることはすぐに見えるタイプの問題なので、全体的に点数の出やすいセットだったと思います。 試験時間120分に対し、 目標解答時間合計は85分。(昨年は110分) すぐに手が動く問題も多いので、解答には余裕があったと思います。ベクトルは係数が少し煩雑で、確率も少し調査が必要ですが、時間的には十分あったでしょう。 ■合格ラインですが、 (そういえば、昨年も、放物線どうしの面積だったのですね^^) (Principle Piece 数学Ⅱ 図形と式 p.47) ※KATSUYAの解いた感想 数学IIの融合問題ってかんじやけど、1つ1つはちょっと簡単かな。原則もまんまで使えるし、落とせない。解答時間5分。 第2問・・・空間ベクトル(正四面体)、内積、三角形の面積(B、20分、Lv.2) 第1問よりも典型的な、正四面体の問題。定数「k」が入っているわけでもなく、すべての点は決定しているので、OA,OB、OCさえ定めておけばすべての長さや内積は出せます。 (Principle Piece 数学B ベクトル p.63) ※KATSUYAの解いた感想 理系と設定が同じの確率ですが、回数がかなり減っており、難易度も大きく下がっています。 ※来年受験する人は、理系の方でぜひといてみてください^^ 理系は8回なげるので、全数調査はちょっときついです。 ※KATSUYAの解いた感想 先に理系の8回を見ているので、余計に簡単。でも、せめて6回じゃない??これまでの問題も簡単やし、4回やったらすぐに書き出せちゃう。解答時間4分。(理系を先に解いているので、参考程度) ☆第4問・・・整数、倍数、方程式の素数解(B、25分、Lv.2) 整数問題です。(1)は理系と共通で、こちらは数学的帰納法ですね^^ (Principle Piece 数学B 数列 pp.50-57) ※KATSUYAの解いた感想 こちらも理系を先に見ているので、(1)は省略。(2)だけやる。・・・理系よりだいぶ答案軽いな^^; どっか間違えたかな? いや間違いようがない(笑) >> 2010年の九大文系数学 以上です^^ 次回は、東北大学(理系)です。
いつもご覧いただきまして、ありがとうございます。 KATSUYAです^^
国公立が試験を開始しました。同時開始なので、すべての大学を即日UP出来ませんが、今の時期は、国公立ラッシュのエントリーになると思います^^;
2015年 大学入試数学の評価を書いていきます。
国立シリーズ、第8弾。
九州大学(文系)です。
難易度の指標は、こんな感じです。
(試験時間120分、4問)
全体総評・合格ライン
第1問 標準的な積分の問題。原則を使えればただの計算。
第2問 四面体と空間ベクトルで、こちらもただの計算問題。係数が煩雑なので、正確に全部出来たかどうか。意外とキーになりそう。
第3問 理系と類似の確率。回数が8回から4回に減っており、かなり負担は軽い。全調査も可能。
第4問 理系と類似の整数問題。こちらも理系よりかなり負担は軽く、(2)はちょっと調べるとすぐにわかる。
時間的にも、3完できそうなセットでしたので、70%は欲しい。
☆第1問・・・2つの放物線で囲まれた部分の面積、軌跡(B、20分、Lv.2)
放物線が絡む面積の問題です。(1)はもちろん判別式、(2)はこちらの原則です。交点が汚いので、この原則は威力抜群。
(Principle Piece 数学Ⅱ 積分 p.29)
(3)は、bを「a」で表していますから、頂点の座標はともに「a」で表されます。媒介変数の軌跡ですから、「a」消去となります。
長さ、内積ともにこれですべて出せます。面積も、それらの値で面積校式を使えばいいですね^^
係数は1/2、1/3、1/4などを2乗するので、結構膨れますね。
the・計算問題きた。これはちょっと完成度が低い問題やな^^; もうちょっとなんかなかったのだろうか。係数だけ煩雑な印象。解答時間9分。
第3問・・・確率、玉の取り出し(B、20分、Lv.2)
4回であれば、最初に青を取れば次が必ず赤であること、など簡単に絞れるものを絞っていくだけで、全数調査可能なレベルです。その上で、1枚もらえるものと2枚もらえるものをピックアップし、確率を出しましょう。
なお、袋の中の赤と青の数は随時変わるので、確率計算には注意。
(2)では理系よりかなりラクな設定になっています。p=2と、それ以外(奇数の素数)のときで分けていけば、どちらもすぐに(p、k)が決定します。奇数の素数のときには、(1)の結果が使えます。
(2)のみで解答時間2分。
対策
対策やお勧めの問題集は、過去の批評を見てください。九大はそこまでの難問はありません。しっかりと典型手法を理解し、それを2,3個組み合わせることができれば、解くことができます^^
>> 2011年の九大文系数学
>> 2012年の九大文系数学
>> 2013年の九大文系数学
>> 2014年の九大文系数学
>> 今年の他の大学も見てみる
■関連するPrinciple Piece■
★ 数学I 2次関数(第1問)
★ 数学II 積分 (第1問)
★ 数学B ベクトル(第2問)
★ 数学A 確率 (第3問)
★ 数学A 整数(第4問)
★ 数学B 数列(第4問)
※受験ランキングに参加しています。「役に立った」という方は、クリックしていただると、すごくうれしいです^^/