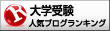いつもご覧頂きまして、ありがとうございます。KATSUYAです^^ 今年の旧7帝大の数学を全て解きおえ、評価をUPしました。理系について、その総括をしたいと思います。
■総括■
1.数学的なセンスを問うような問題が増加
新課程の整数に代表されるように、「こういう問題ならこう」と、一瞬で解法が判断できるような問題というより、「考え、調べ、規則を発見する」といった数学的なセンスを磨いているかどうかを見る問題が増えたように思います。従って、根本的な事柄をきちんと理解している人にとっては、全体的に簡単に感じたかもしれません。
2.新課程の複素数平面は出題が本格化
旧7帝大では、複素数平面が待ってましたとばかりに出題され始めました。昔のストックがあるのかもしれません(笑) 応用的な問題もありますが、まだ典型パターンが多い印象。図形的な考察を絡めないと難しいような問題は見受けられませんでした。
3.整数問題は、絞ってから調査することが有効なタイプが目立つ
整数が単元かされたことで、因数分解系など、テクニック1発で出来るタイプは減り、「指数は多項式よりも増加が早い」といった感覚を利用することで予想をし、それを自ら証明して絞る、という流れのものが目立ちました。
■難易度順位■
ここからは、難易度順位をまとめます。
1.各問題の難易度
2.解答までの時間
3.制限時間との兼ね合いを考慮した、得点のしにくさ。
これらを総合的に判断した結果の順位です。大問ごとに5ポイント満点で点をつけ、問題数で平均しています。
※ポイントの数値は相対的なものであり、0.2ポイント以上違えば、難易度の差が感じられるものと思ってください。
逆にいえば、それ以内の場合は、難易度の違いは人によります。
2016年 旧7帝大 理系リーグ
( )内は、昨年からの順位変動、および2012年~2015年のポイントの順)
※なお、東工大は3.04 pt です。
特記すべき事項をいくつか。
名古屋大学は2年連続、東京大学に迫る勢いで2位です。昨年のようにどれも解けないことはありませんでしたが、最後の問題の難易度が非常に高かったです。東大は安定して3ポイント越えで、適度な難問と適度な応用問題で構成されています。ただし、1位~4位は団子状態で、どれも非常に骨のある良問セットだったと思います。
東北大が最下位に転落。前半の4問が非常に軽かったため、非常に点数を稼ぎやすいセットになりました。北大は全体的に例年より難しく、5位に浮上です。九大は確率等が文系より簡単で、文系のセットより点数が取りやすいです。
以上です^^